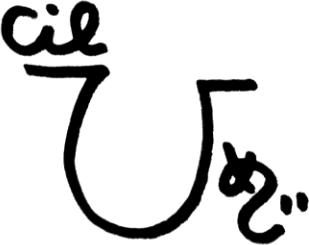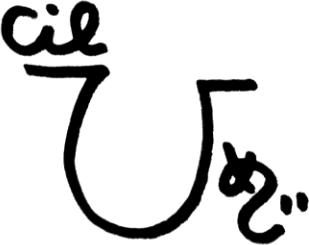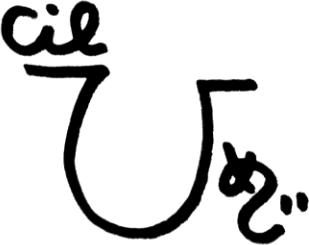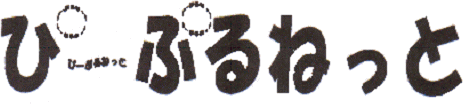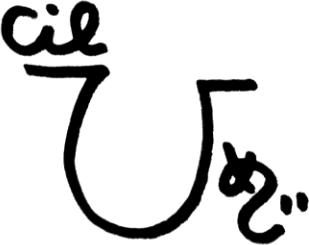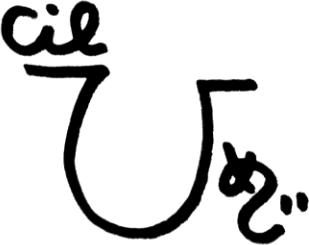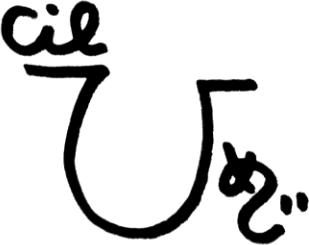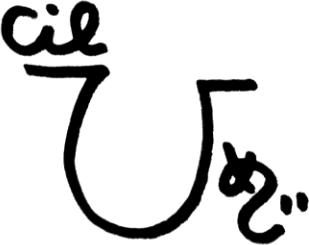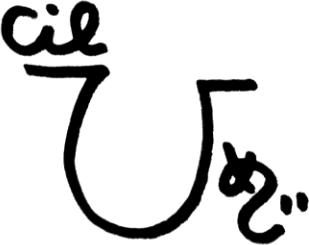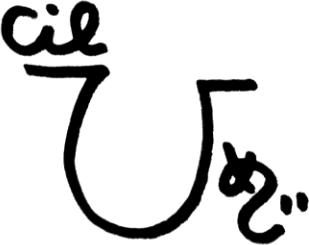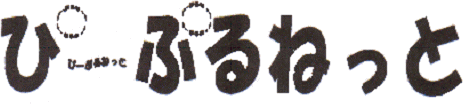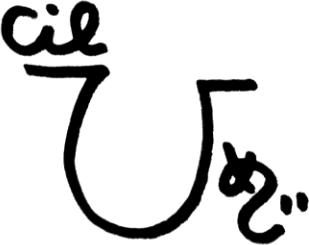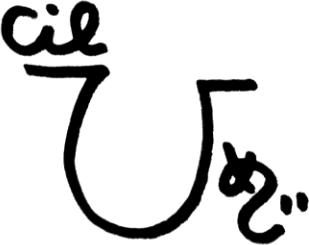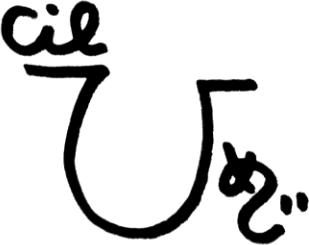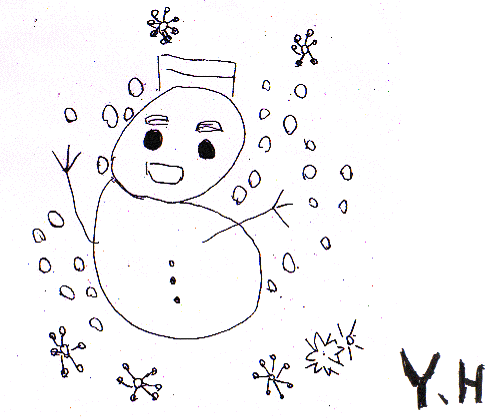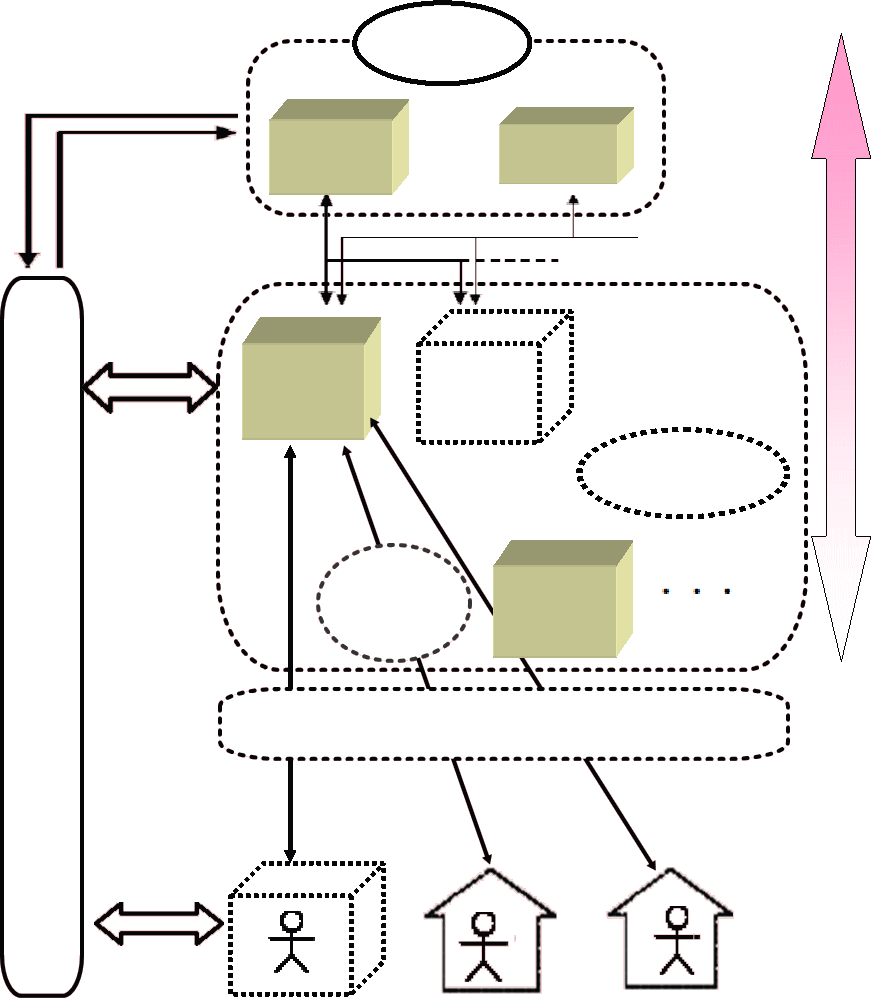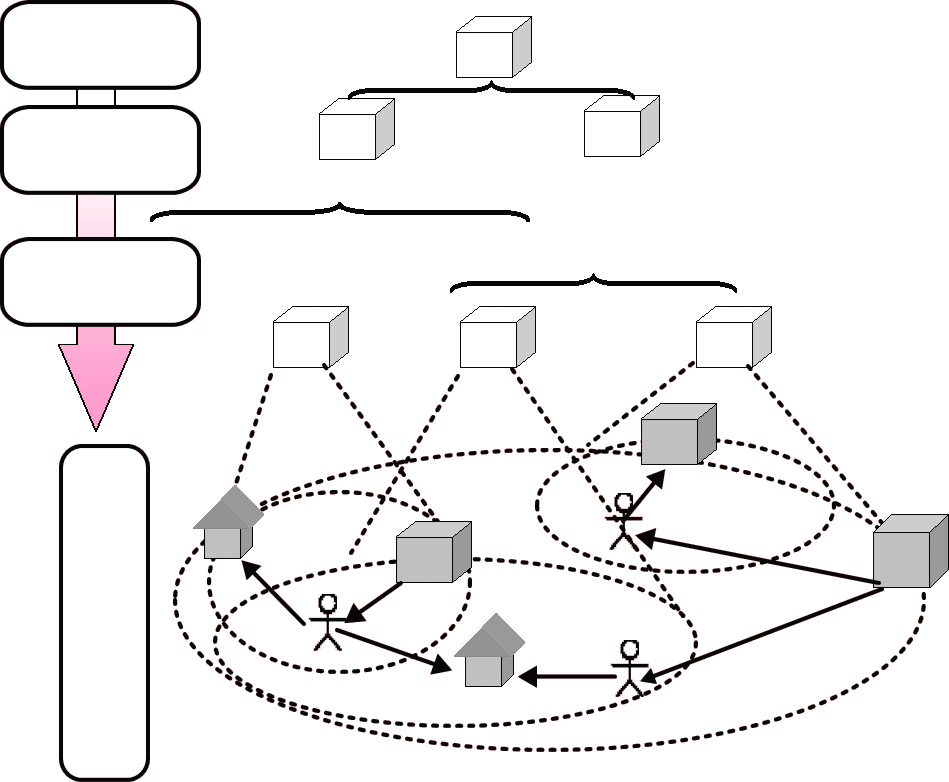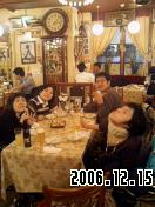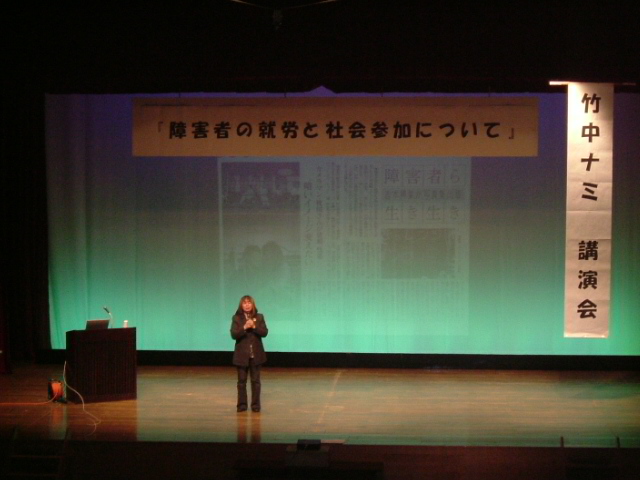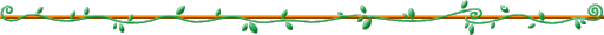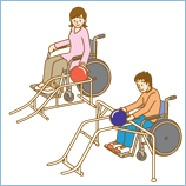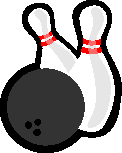障害者自立支援法について
(理事 河原正明)
新しい年を迎えて、皆様いかがお過ごしですか? 昨年を振り返ってみますと、障害者自立支援法が平成17年11月7日に制定され、18年4月に一部施行。10月に本格的施行と私たち障害福祉に携わるものにとっては、まさしく「自立支援法に明けて自立支援法に暮れた」一年であったように思います。
一体、障害者自立支援法は私たちの生活に何をもたらしたのでしょうか?大変、複雑多岐にわたる法律ですので、一様に語ることは出来ませんが、紙面の許す範囲で検証してみます。
<財源問題と自己負担>
利用者サイドから自立支援法で何が変わったかを聞いた時、多くの方が口にされるのが「サービス利用料の負担の増加」です。しかし、その中身を良く聞いてみると大きく2つに分かれるように思います。まず、ホームヘルプなど居宅サービスを中心に利用されている方からは、「今まで、掛からなかったサービス料が、1割定率負担で急に利用料が増えた。」という意見です。一方、施設を中心に利用されている方の感想は少し違います。「何をしてもお金が掛かるようになった。」という意見です。今までも施設では利用料は存在していたのですが、通常の生活に掛かる食費や光熱費または、送迎や旅行費用など通常のサービスに含まれない費用も支援費で賄われていた部分があるためかと思います。いずれにせよ、一部の児童の方を除いては、サービスの利用負担が増えたことは事実です。
しかし、負担がある事が全ていけないことだとは思いません。障害があっても正当な権利を得るための適正な負担はするべきだと思います。問題は負担のあり方ではないかと思うのです。まず、今回の制度では、原則としてサービス量に応じた定率の負担ですので、重度で低所得の方の負担感が強くなるシステムになっています。一見、定率負担はサービス利用という視点では公平であるように思えますが、本来の目的であるノーマライゼーションというところに視点をあてたときに、本当に公平だといえるでしょうか?「あたりまえの生活を送るためのリスク」を公平に分担することが福祉だと考えていた私には、どうも納得のいかないところです。
もうひとついえることは、適正な負担が出来る環境整備が無いことです。今回、国では特別な補正予算を組み負担増の救済法として、さらに負担上限を段階式に減額したり、減免の社会福祉法人枠を撤廃する予定であり、自治体においても独自の減額を設けています市町があります。しかしこれでは、まるで障害者という特別枠にさらに低所得という特別枠を作るというようなもので、これも、ノーマライゼーションの理念からすれば、如何なものかと思います。もし、それだけの財源があるとするなら、所得保障に廻されるべきではないかと私は思います。
利用者の方が、この自立支援法に負担額以上の負担感を感じる方が多いのは、額の多さではなく、システムの不条理からくるものだと思います。
<障害程度区分と利用サービス>
負担の次に話題が多いのが障害程度区分です。まず、「あの106項目の調査で適正な障害程度が表せるのか」という意見です。これについてまず、私が思ったのは、名称が悪かったということです。「障害程度区分」というのが大きな誤解を生んだと思っているのです。これが「障害者のための介護程度区分」なら、ほぼ適正な範囲の調査ではないかと思うのです。つまり、今回明らかにされたのは、日常生活に必要な介護時間であって、決して、社会参加の部分の支援や障害の状況を表すものではないということです。ですから、介護の定義で曖昧な環境整備や声かけ、見守りの支援が中心である知的障害や精神障害の方には、結果も曖昧な点が見受けられるのだと思います。
よって、この区分は介護給付にしか適用されませんし、姫路市においても区分とサービス量は直接的に比例するものではないことを明言しています。では、この障害程度区分は、なんのために設けられているのでしょうか?まず、区分によって使える介護事業を限定すること。そして、区分によって報酬単価に差を設けたことです。つまり、これによって事業所の皆さんは利用者選びをしなければいけなくなったことです。特に生活介護では、区分1の差が、年間収入に大きな影響を及ぼすことが予想されます。
この自立支援法の大きな目的には精神障害の方のサービス資源の充実が上げられていますが、この障害区分の使い方を見る限り、比較的区分が低く、専門的支援が断続的に必要な精神障害の積極的な受け入れが可能なのか、とても危惧されます。
<総合的な相談システムの確立>
後は、私が障害者自立支援法で一番気になることを書きたいと思います。まず、今回、サービスが再編されるとともに規制緩和によって小規模で多機能な事業が展開できるようになったことは、障害者が自立した地域生活を送るには、大変プラスになると思います。しかし、それには様々なサービスを複合的に利用することが想定されますが、残念ながら現状では、施設を始め関係する事業所への依存が強く、利用者の主体的なサービス利用までには至っていません。
つまり、障害者ケアマネジメントの有無、良し悪しが障害者の暮らしに大きく関与していると思うのです。それには自立支援法に基づく相談支援事業を有効に活用し、姫路市独自の総合的な相談システムの確立が望まれるところです。
すでに青写真として具体的な例が、姫路市地域福祉計画並びに障害者計画において示されていますのでご紹介します。
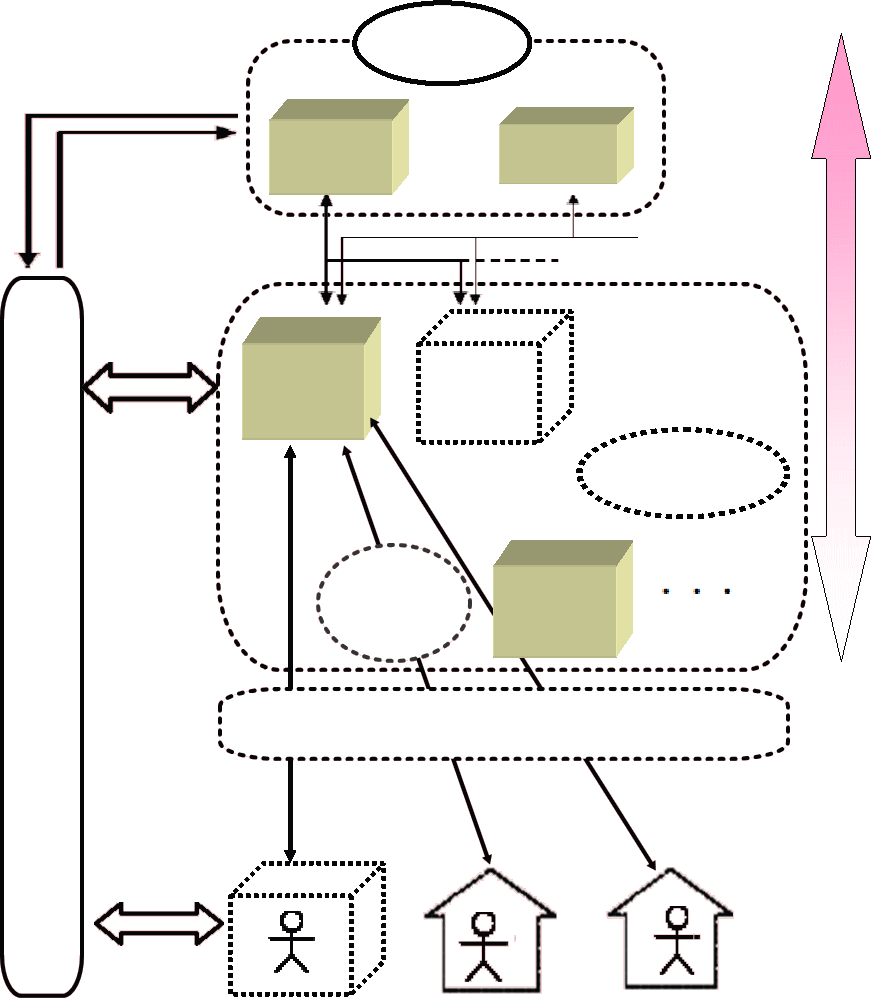
中枢・専門機能
(1ヶ所)
総合福祉
通園センター
保育所
支援内容の助言
経済的助言 等
情報提供
支援内容の報告等
情報提供
技術的助言
訪問調査・支給決定
利用調査・あっせん
利用援助・苦情対応
保健福祉
サービス
センター
保健福祉
サービス
センター
地域拠点機能等
障害者団体
・
相談員 等
在宅介護
支援
センター
日常的な相談支援
(施設)
(在宅)
(在宅)
障害福祉課
高度・専門
一般・個別